
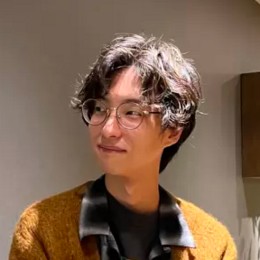
島尻 亮汰
Mitsuri PdM
製造業向け商取引プラットフォーム「Mitsuri」のプロダクトマネージャーとして、プロダクトの開発からマーケティングの戦略立案・実行に至るまでを包括的にマネジメント行なっている。著書「SaaSで考えるPLG戦略」
製造業においてDX(デジタルトランスフォーメーション)は大きな期待を集めていますが、成功例がある一方で、残念ながら失敗に終わるケースも少なくありません。
なぜ製造業DXは失敗してしまうのか?今回はその主な理由と、失敗を避けるためのポイントを詳しく解説していきたいと思います。
多くの企業がDXを「デジタル化」という漠然とした目標で始めがちです。
具体的な成果やビジョンが不明確なまま進めると、導入後の効果が曖昧になり、結果としてDXが頓挫します。
また、「DXをやらなければいけないから」といった受動的な動機で進める場合、現場や経営層のモチベーションも低下し、結果として中途半端な形で終わってしまう可能性が高まります。
解決策: DX導入の目的を「生産性向上」「リードタイム短縮」「品質向上」など具体的に設定し、達成基準や評価指標を明確化しましょう。
経営層がDX推進を決定しても、現場の理解や協力が得られないと成功は難しくなります。とくに製造現場では、慣れ親しんだ業務プロセスを変えることへの抵抗感が強くなりがちです。
現場の抵抗感の理由として、「デジタル化で自分たちの仕事がなくなるのではないか」「新しいシステムを覚えることが負担になる」という不安が挙げられます。
解決策: 現場スタッフを巻き込み、DXの必要性や具体的なメリットを共有する場を設けることで、意識のギャップを埋めましょう。また、経営層が現場の意見を積極的に取り入れる姿勢を示すことも重要です。
全社規模で一度にDXを進めようとすると、複雑性が増し管理が難しくなります。また、初期段階の投資が膨らみすぎて経営的な負担になることもあります。さらに、最初から大きな変革を目指すと、問題が発生した際のリスクも大きくなります。
解決策: 小規模なパイロットプロジェクトから始め、成功例を作ってから段階的に拡大するアプローチが有効です。成功事例ができれば、それを元に社内の理解や協力を得やすくなります。
導入するシステムが業務や業界特性に合っていない場合、思ったような効果が出ず、かえって業務が複雑になることがあります。また、現場の意見を十分に反映せずに選定したシステムは現場で受け入れられず、定着しないケースも見受けられます。
解決策: システム選定では現場の要件を明確化し、複数のソリューションを比較検討して適合性を確かめましょう。現場のユーザーが実際に触れる機会を設け、フィードバックを得るプロセスも重要です。
製造業におけるDXは、新しいITツールやシステムを使いこなせる人材が不可欠です。人材育成が追いつかないと、導入後の活用が不十分となり、投資が無駄になるリスクがあります。
さらに、外部の専門家やITベンダーに依存しすぎると、自社内にノウハウが蓄積されず、持続的な改善が難しくなります。
解決策: 研修や外部パートナーとの連携を活用し、DX推進人材の育成や確保を戦略的に進めましょう。また、外部パートナーとの連携を通じて自社内にも知識やノウハウを積極的に蓄積することが重要です。
DXは一度導入して終わりではありません。導入後も継続的な改善やアップデートを行わないと、最初の効果が徐々に薄れ、最終的には形骸化してしまいます。
解決策: PDCAサイクルを定着させ、定期的な評価や改善を行う仕組みを確立しましょう。定期的なレビュー会議を設け、現状の課題や改善策を議論することも有効です。
DXの失敗を避けるためには、目的の明確化、現場との連携、小さな成功事例の積み重ね、適切なシステム選定、人材育成、そして継続的な改善が非常に重要です。
製造業DXの推進において、これらのポイントを意識して進めていきましょう。
私たちCatallaxyでは、DX共創事業を通じてオーダーメイドの受発注システム構築を支援しています。
企業が持つ独自のノウハウをシステム化し、DX環境の構築を伴走します。受託開発、自社プラットフォームサービス、工場経営、商社事業、クラウドサービス開発など幅広い分野で培った豊富な経験とスキルを活用し、お客様のデジタル化を迅速かつ総合的にサポート。
各企業が抱える特有の課題をテクノロジーを活用して解決に導きます。
こちらからぜひ気軽にお問い合わせください。

Mitsuriでどんな取引が行われている?
新しい機能を使ってどう新規取引につなげる
そんな疑問に毎月メールでお届けします