
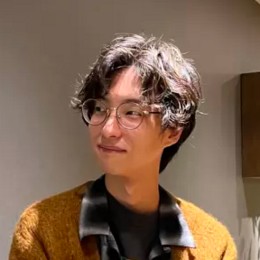
島尻 亮汰
Mitsuri PdM
製造業向け商取引プラットフォーム「Mitsuri」のプロダクトマネージャーとして、プロダクトの開発からマーケティングの戦略立案・実行に至るまでを包括的にマネジメント行なっている。著書「SaaSで考えるPLG戦略」
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が盛んに使われるようになって久しくなりました。
経済産業省の提言や大企業各社の「DX宣言」、そして多額のIT投資。表面的には、日本企業もデジタル化に向かって歩みを進めているように見えます。
しかし、現場を覗いてみるとどうでしょうか。FAXの送受信は日常的に行われ、紙の帳票が回覧され、エクセルファイルがメールで飛び交っています。「DXを進めているはずなのに、なぜ現場は変わらないのか?」という疑問を抱いたことのある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「なぜ大企業のDXは進まないのか」という問いに対して、表面的なスキルやツールの問題ではなく、もっと根深い“構造”や“文化”の視点から考えていきます。
大企業で新しい仕組みを導入しようとすると、必ずといっていいほど稟議や承認フローの壁が立ちはだかります。
企画部門、情報システム部門、法務、経理、役員会など、数多くのステップを経る必要があり、その間に現場の熱意が失われてしまうことも少なくありません。
変化を推進するにはスピードと勢いが欠かせませんが、意思決定の遅さが変革の芽を摘んでしまうことが多いのです。
多くの企業では、経営層がDXを推進すると宣言し、社内に向けて立派な資料を展開します。
しかし、現場が求めているのは「紙の申請書を減らしたい」「発注確認をもっと簡単にしたい」といった具体的で切実な改善です。
経営と現場の間に橋渡しがなければ、DXはただのスローガンで終わってしまいます。
「うちのことはベンダーが一番わかっている」。そんな言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
システム導入や改善を外部のSIerに丸ごと委ねる体制は、一定の安心感をもたらしますが、同時に「自分たちで業務を変えていく力」を奪ってしまいます。
結果として、複雑にカスタマイズされたシステムが“触れてはならない存在”となり、変革の柔軟性を奪っていきます。
導入から10年、20年が経った基幹システムが、今も企業活動の中核を担っているという例は珍しくありません。
システムには多くのノウハウや歴史的なデータが蓄積されており、それ自体が貴重な資産です。
しかし、この「壊したくない・壊せない」という心理が変化への最大の障壁となります。変えるためには膨大な手間とリスクがかかり、結果的に「今のままでいい」という選択が繰り返されてしまうのです。
情報システム部門が新しいツールを導入しようとしても、「それは業務部門の責任」とされ、業務部門が改善を訴えても「システムのことは情シスへ」と返される。
こうした構図の中で、DXは「誰のものでもない取り組み」になってしまいます。
部門ごとに目標や評価軸が異なる大企業では、全体最適よりも部分最適が優先されがちです。これが、DXの推進をより難しくしています。
大企業では、新しい提案が「過去に例があるか」「他社はどうしているか」と問われる場面が非常に多くあります。
これは一見、合理的なリスク管理に見えますが、実は変革の芽を摘む構造でもあります。
変革には“前例のない挑戦”がつきものですが、それが評価されにくい文化の中では、誰も一歩を踏み出そうとしなくなってしまいます。
DXは、試行錯誤と小さな失敗を繰り返しながら進めていくものです。
しかし、「失敗しないこと」が評価される環境では、新しいことに挑戦する人ほどリスクを背負い、評価されないという矛盾が生まれます。
結果として、現場では変化を避ける空気が広がり、何も動かないまま時間だけが過ぎていくのです。
「DXが進まないのは、現場のリテラシーが低いから」「人材不足だから仕方ない」──そうした言い訳で片づける前に、私たちはもっと深く、構造や文化の問題に目を向ける必要があります。
変化を拒んでいるのは、技術ではなく人と組織のあり方そのものかもしれません。
それでも、どこかで誰かが小さな一歩を踏み出すことからしか、未来は変わらないのです。
私たちCatallaxyは、こうした「変えたくても変えられない」現場に伴走し、部門横断の対話設計や業務起点での変革支援を通じて、現実的で持続可能なDXを実現してきました。
テクノロジーを“導入する”のではなく、組織が“使いこなす”ことができる状態を共に作ること。それが、私たちの考える「共創型DX」です。
もし貴社が、DX推進のどこから手をつけるべきか迷っているなら、ぜひ一度、Catallaxyにご相談ください。現場に根ざした解像度で、最初の一歩を一緒に描くお手伝いをします。
こちらからぜひ気軽にお問い合わせください。

Mitsuriでどんな取引が行われている?
新しい機能を使ってどう新規取引につなげる
そんな疑問に毎月メールでお届けします