
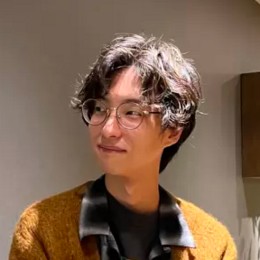
島尻 亮汰
Mitsuri PdM
製造業向け商取引プラットフォーム「Mitsuri」のプロダクトマネージャーとして、プロダクトの開発からマーケティングの戦略立案・実行に至るまでを包括的にマネジメント行なっている。著書「SaaSで考えるPLG戦略」
受託製造業への見積もり依頼は、発注企業が外注したい製品や部品の図面を提示し、供給企業(受託製造業)から金額や工期の提案を受けるプロセスです。
理想は品質が良く、安価で、短納期ですが、依頼方法が曖昧だと、余計なやり取りやトラブルが発生します。
短時間で円滑に取引を成立させるためのポイントを見ていきましょう。
見積もり依頼の基本は「内容」と「範囲」を具体的に示すことです。
図面通りなのか、一部工程だけなのか、材料支給や表面処理の有無など、依頼範囲をはっきりさせましょう。
とくに溶接や表面仕上げは曖昧になりがち。希望する仕上がりイメージを写真や見本で伝えることで、トラブルの予防になります。
複雑な製品の場合は、可能な限り3Dデータを提供することで見積精度が向上します。
製作数量(ロット数)とリピート頻度を明確にすることも重要です。ロット数が多ければ量産効果で単価は下がります。
発注頻度も供給企業にとっては工程管理の大きなポイントです。
単発案件かリピート案件かを明確にし、リピートの場合は初期投資を抑える提案も可能になります。予備在庫を準備することで、納期管理が容易になることもあります。
納期だけでなく、発注予定日もセットで伝えることが肝心です。
供給側の準備期間を確保するためにも、発注タイミングを明示することをおすすめします。
社内手続きが長引く場合は、内示によって製作準備を進めてもらう方法もあります。
希望単価や実績単価を伝えることは、双方にとってメリットがあります。
単価が合わず発注しない状況を避けるためにも、見積もり依頼時に希望する価格帯を伝えることで無駄な手間を省けます。
また、相見積もりを取る場合は必ずその旨を伝えましょう。後出しは信頼関係を大きく損ねるリスクがあります。双方が協力してコストダウンを考える姿勢が重要です。
洗浄、梱包、配送方法、支払い条件、初期費用の取り扱いなど、細かな条件を明示しておくこともトラブル防止につながります。
とくにNG品が出た場合の対応方法を明確にしておくことで、後々の揉め事を回避できます。
近年、約束手形廃止の動きもあり、電子記録債権(でんさい)の利用が増えています。双方に負担のない条件での取引を事前に確認しておくことが大切です。
見積もり依頼は受託製造業者にとっても大きな労力がかかる作業です。見積もりだけで発注しない企業は信頼を損ない、最終的に見積自体を受けてもらえなくなる可能性もあります。
現在、受託製造業者の数は減少傾向にあり、高付加価値化を目指す企業が増えています。
かつてのような発注者優位の状況は変わりつつあり、供給側も発注側を選ぶ時代になっています。
丁寧なコミュニケーションと明確な条件提示を行い、一社ずつしっかりとした信頼関係を築くことが、安定した調達や取引成功への最短ルートなのです。
Mitsuriは製造業界向けのマッチングプラットフォームとして、依頼内容の明確化から見積もり依頼までをオンライン上で簡単かつ迅速に行えます。
図面や、条件提示、希望単価の設定も非常に簡単で、コミュニケーションのロスを削減します。
無料登録で使えますので、ぜひ効率的な見積もり依頼を体験してみてください!

Mitsuriでどんな取引が行われている?
新しい機能を使ってどう新規取引につなげる
そんな疑問に毎月メールでお届けします